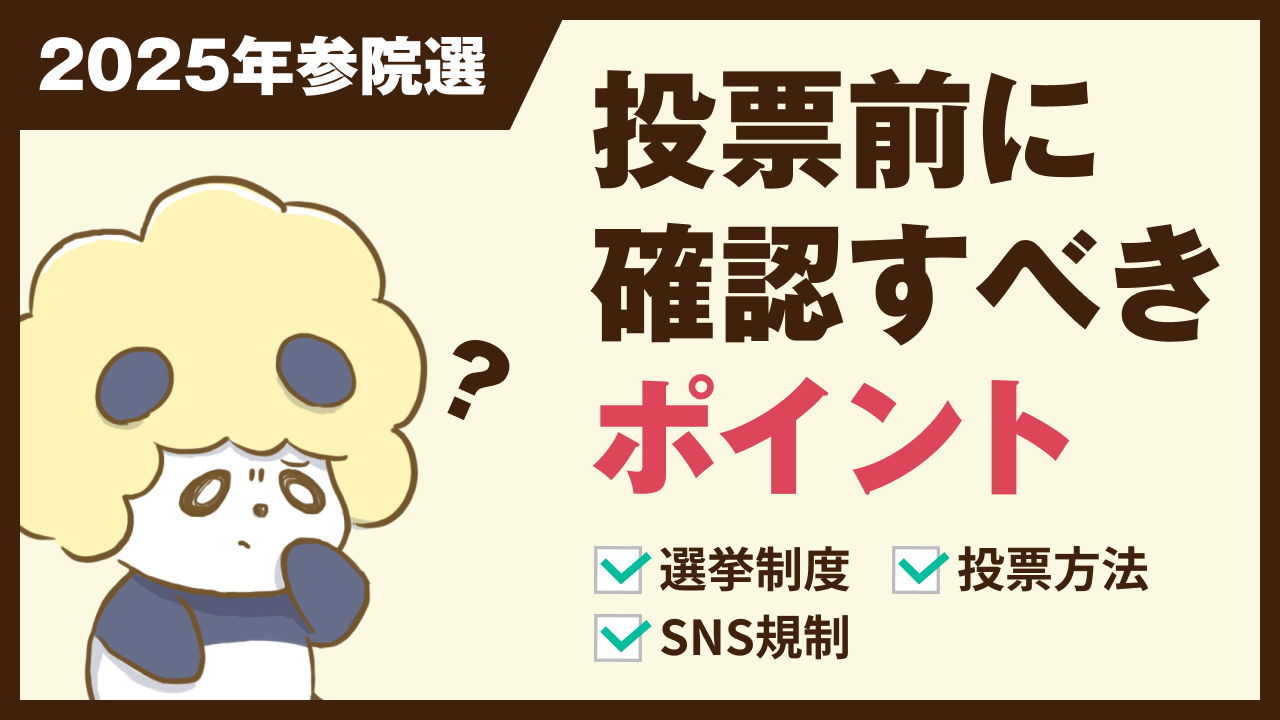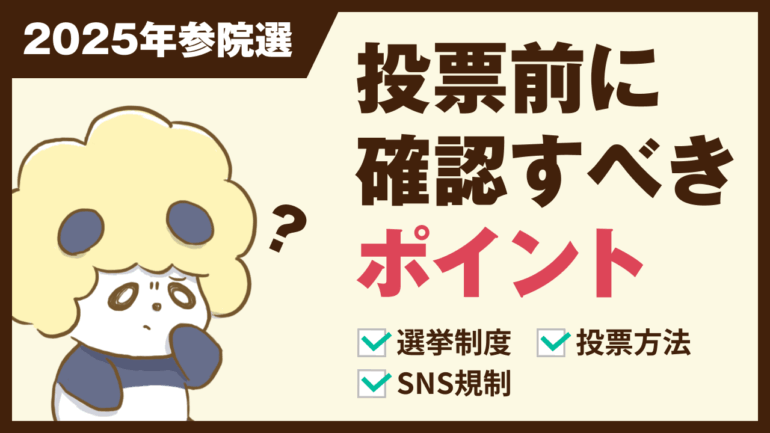7月20日に第27回参議院議員通常選挙が行われます。昨年10月に実施された衆議院選挙で与党が過半数を下回ったことにより、参議院の重要性が高まっているいま、参議院選挙に高い注目が集まっています。注目の参議院選挙について、選挙制度や投票方法、衆院選との違いまで本記事ひとつで徹底解説します。
2025年参議院選挙の国政への影響
2024年10月の衆議院選挙は、政権を担う自由民主党(自民党)・公明党の連立与党の議席数が過半数に届かない少数与党という結果になりました。それにより、今回の参議院選挙の結果が国会運営に与える影響が高まっています。
現在の参議院・衆議院における与野党の議席
現在の衆議院では、自由民主党・無所属の会が196議席、公明党が24議席を占めており、与党全体では220議席となっています。一方、野党第1党の立憲民主党・無所属は148議席を有しており、いずれの勢力も過半数である233議席には達していません。
これに対し、参議院では自由民主党が113議席、公明党が27議席を占め、与党が計140議席と過半数を占めています。
法律成立への影響
法案が衆議院で過半数の賛成を得て可決、参議院でこれと異なった議決をした場合、衆議院で3分の2以上が賛成し再可決されれば、法律として成立します。
しかし、少数与党となっている現在、衆議院で3分の2以上の賛成を得ることは複数の野党の協力がなければ難しいと考えられます。すなわち、衆議院で過半数の賛成で可決したとしても、参議院で可決されなければ法律の成立が困難な状況です。そのため、参議院で与党が過半数を維持するかどうかは、今後の法律成立に大きな影響を与えます。
少数政党の役割
2024年衆議院選挙後、最大野党である立憲民主党ではなく、少数野党である日本維新の会(議席数38議席)や国民民主党(議席数28議席)がキャスティングボード(決定権)を握ると言われました。これは、衆議院選挙直後の自民党・公明党が合計215議席であり、国民民主党が自民党・公明党の政策に合意した場合、過半数の233議席を超えるためです。実際に、令和7年度予算案は、日本維新の会が求めた高校無償化を盛り込むことで、日本維新の会と与党が合意し可決されました。
同様に、参議院での法案可決が重要になっている現在、与党・野党第1党以外の日本維新の会や国民民主党などの参議院選挙における獲得議席が国会運営に大きく影響する可能性があります。
参議院選挙の仕組み
では、具体的に参議院選挙はどのような仕組みで行われるのでしょうか。参議院選挙は、3年に1度、議員定数248議席の半数124議席を改選する選挙です。124議席のうち74議席が選挙区で、50議席が比例代表で選出されます。
選挙区
参議院選挙の選挙区は、基本的に都道府県ごとにわかれています。ただし、一票の格差(選挙区ごとに当選者1人を選出するための有権者数が異なるために、一票の重みに差が生まれるという問題)を是正するため、2016年の参院選から、島根と鳥取、徳島と高知は2県で一つの選挙区となる合区となっています。
比例代表
比例代表制では、各党の得票数を1,2,3…と整数で割っていき、その商が大きい順に当選者を決めていく「ドント式」という方法によって、各党に議席が割り当てられます。
以下の表は、架空の定数9議席の比例代表選挙区における「ドント式」の議席配分の計算例です。この例では、A党が3議席・B党が3議席・C党が2議席・D党が1議席を獲得します。
|
政党名 |
A党 |
B党 |
C党 |
D党 |
|
総得票数 |
2000 |
1800 |
1300 |
1000 |
|
1で割る |
2,000 当選① |
1,800 当選② |
1,300 当選③ |
1,000 当選④ |
|
2で割る |
1,000 当選④ |
900 当選⑥ |
650 当選⑧ |
500 |
|
3で割る |
667 当選⑦ |
600 当選⑨ |
433 |
333 |
|
4で割る |
500 |
450 |
325 |
250 |
|
当選者数 |
3 |
3 |
2 |
1 |
参院選の比例代表には、以下の特徴があります。
- 全国を1ブロックとする
- 候補者名、政党名のいずれでも投票できる
- 「非拘束名簿式」が適用される
- 「特定枠」がある
参議院選挙の比例代表は、候補者名・政党名のいずれでも投票することができます。各政党の比例議席獲得数は政党全体での票数(政党名での票・その政党から比例代表に立候補した全候補者名での票数)により決まりますが、政党内での当選者は、候補者名で投票された票数が多かった順に決まる、「非拘束名簿式」が適用されます。
ただし、「特定枠」という、候補者の得票数に関わらず、政党が優先的に当選させたい人を決めておくことができる制度があります。特定枠は、「合区」となった選挙区で、あぶれてしまう議員を比例代表で救済する狙いを背景に、2019年の参議院選挙から導入されました。
2022年参議院選挙では、自民党が2名、れいわ新選組が1名、ごぼうの党が8名、特定枠を利用しました。
参議院選挙と衆議院選挙の違い
参議院選挙と衆議院選挙の選挙の仕組みには、以下のような違いがあります。
| 参議院選挙 | 衆議院選挙 | |
| 時期 | 3年に1度半数を改選 | |
| 選挙制度 | 選挙区制(45区72人) 比例代表制(1区50人) |
選挙区制(289区289人) 比例代表制(11区176人) |
| 比例代表制の名簿 | 非拘束名簿式 (投票用紙には政党名または候補者名の記入) |
拘束名簿式 (投票用紙には政党名のみ記入) |
| 重複立候補 | 不可 | 可 |
| 被選挙権 | 満30歳以上 | 満25歳以上 |
まず、任期と実施される時期についてです。
衆議院議員の任期は4年間であり、任期満了の場合は4年に1度、全465議席について一斉に衆議院選挙が実施されます。衆議院は内閣による解散があるため、4年より短い間隔で衆院選が行われる場合もあります。
一方で、参議院議員の任期は6年間であり、解散がありません。そのため、必ず3年に1度、議席の半数を対象に参議院選挙が実施されます。参議院は衆議院に比べ任期が長く、解散もないため、一時的な世論や内閣の動向に左右されず長期的な視点で議論ができるという利点があることから、「良識の府」と呼ばれます。
また、選挙制度にも違いがあります。
衆議院選挙は小選挙区制と比例代表制であるのに対し、参議院選挙は選挙区制と比例代表制です。
衆議院選挙の小選挙区制では、ひとつの小選挙区で1人しか当選しません。一方、参議院選挙の選挙区制では、1回の選挙でひとつの選挙区あたり、1~6人が当選します。
衆議院選挙の比例代表では、ブロックが全国で11ブロックにわかれています。一方で、参院選では、全国でひとつのブロックです。また、衆議院選挙では、政党が候補者の当選順位を事前に決めた名簿を提出し、有権者は政党名のみで投票する「拘束名簿式」がとられているのに対し、参議院選挙では、有権者は政党名もしくは候補者名で投票し、政党内での個人の得票数が多かった順に当選者が決まる「非拘束名簿式」がとられています。
また、衆議院選挙では、小選挙区と比例代表の重複立候補が認められており、小選挙区で落選し比例代表で当選する復活当選があります。しかし、参議院選挙では、重複立候補は認められていません。
被選挙権が与えられる(立候補できる)年齢は、衆議院選挙が満25歳以上なのに対し、参議院選挙は満30歳以上です。
参議院選挙と参議院補欠選挙の合併選挙
2024年東京都知事選挙に当時参議院議員だった蓮舫氏が出馬し、蓮舫氏は参議院議員を自動失職しました。蓮舫氏の自動失職による東京選挙区の欠員を補うため、補欠選挙が今回の参議院選挙に組み込まれ、合併選挙となります。
東京選挙区では、改選6議席+非改選1議席(欠員分)の7議席が争われます。
得票数が6位までの当選者は任期が6年ですが、7位での当選者には非改選分の議席が割り当てられるため、任期は3年になります。
有権者のSNSの注意点
参議院選挙への関心が高まってくると、SNSで選挙に関わる発信をする方もいるでしょう。しかし、特定の候補や政党の当選を目的とした選挙運動は実施してよい期間が公職選挙法により定められています。
選挙運動が許されている期間
特定の候補者や政党への投票を呼びかける行為は、「選挙運動」と呼ばれます。「選挙運動」ができる期間には制限があり、公職選挙法において公示日から選挙前日までの「選挙運動期間」のみ、認められています。
公示日前に「次の参院選では〇〇党へ一票を!」「立候補予定の△△候補を応援しよう!」と発信することは「事前運動」とみなされ、公職選挙法により禁じられています。
選挙当日に気をつけること
選挙当日(投開票日/選挙期日)は選挙運動期間ではありません。
選挙当日へと日付が切り替わった瞬間に、X(旧Twitter)やInstagramで「△△候補に投票しよう」と投稿したり、「比例代表は〇〇党と記入を!」とブログを更新したりすることは禁止になります。LINEなどで直接、友人に「△△候補に投票してね」とメッセージを送ることも禁止されています。
また、選挙当日は、選挙前日までに投稿された『特定の政党・候補者への投票依頼』に該当する投稿を拡散する行為(いいね・リポストなど)も控えましょう。
投票そのものを呼びかける場合
特定の政党・候補者への投票依頼ではなく、一般有権者が「投票に行こう!」と選挙への参加そのものを促すことは選挙運動に該当しないため、選挙当日に行うことができます。
ただし、特定政党・候補を支持する団体などが組織的に投票への参加の呼びかけを行うと、公職選挙法違反となる恐れがあります。
また、選挙当日に投票に行ってきたことをSNS上で報告する場合は、投票先を明らかにしないようにしましょう。