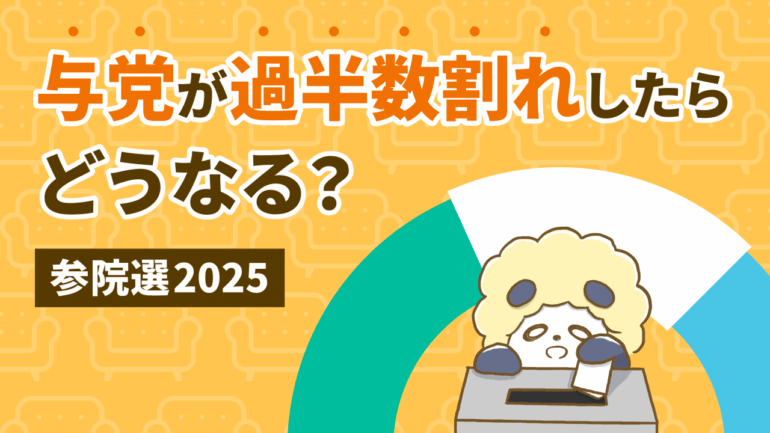2024年の衆議院選挙で与党が過半数を割る結果になったことにより、参議院が果たす役割が高まっています。7月20日投開票の参議院選挙で各党が獲得する議席数が政局にどのような影響をもたらすのか解説します。
2025年参議院選挙は与党の過半数維持が注目ポイント
2025年参議院選挙の焦点は、自由民主党(自民党)・公明党の連立与党の合計議席数が過半数を維持できるかどうかです。
参議院における過半数維持の重要性は?
参議院で与党が過半数の議席を維持するかどうかは、今後の国会運営を左右します。
国会は、参議院と衆議院の二院制で成り立っています。予算案や法案は、両院で審議・議決されます。現在の衆議院は、自由民主党・無所属の会と公明党の合計議席数は220議席と過半数の233議席を下回っており、与党のみでは予算案や法律案を可決することができない状況です。一方の参議院は、現在、与党が140議席と過半数の125議席以上を占めていますが、今回の参議院選挙で参議院も与党が過半数を割った場合、さらに安定した政権運営が難しくなる見通しです。
【現在の参議院勢力分布】(2025年6月現在)
◆与党:計140議席
– 自由民主党:113議席(改選52議席、非改選61議席)
– 公明党:27議席(改選14議席、非改選13議席)
◆野党:計100議席
– 立憲民主・社民・無所属:41議席(改選23議席、非改選18議席)
– 日本維新の会:17議席(改選5議席、非改選12議席)
– 国民民主党・新緑風会:12議席(改選5議席、非改選7議席)
– 共産党:11議席(改選7議席、非改選4議席)
– その他野党・会派:19議席(改選11議席、非改選8議席)
※参議院の定数は248議席(現在欠員8議席)、過半数は125議席
与党は125議席中50議席獲得で過半数維持
参議院は3年ごとに半数が改選されますが、本来非改選の東京選挙区1議席の補欠選挙も同時に実施されるため、今回の参議院選挙は125議席(選挙区74議席・比例50議席・東京選挙区欠員補充1議席)が対象となります。
与党の非改選議席は74議席(自由民主党61議席・公明党13議席)であり、与党が過半数を維持するためには、今回の参議院選挙で争われる125議席中50議席を獲得する必要があります。これは全改選議席の40%にあたり、与党がこの40%以上の議席を確保するか否かが、選挙結果の分かれ目となります。
「衆議院の優越」と参議院の議席数の関係
ここでは、現在の衆議院の勢力図によって、参議院が国会運営に与える影響力が高まっていることを「衆議院の優越」を踏まえて具体的に解説します。
「衆議院の優越」とは
国会は、衆議院と参議院の二院により成り立っていますが、両院の議決が異なる場合もあります。その際は、両院協議会等で両院の意思の擦り合わせが試みられますが、それでも一致しない場合、いくつかの点で衆議院の議決が優先されるなど、衆議院により強い権限が憲法で認められています。これを、「衆議院の優越」と呼びます。
具体的には、「条約の承認」「内閣総理大臣の指名」「予算の議決」「法律案」について衆議院の優越があります。
「衆議院の優越」と法律成立における参議院の影響力
衆参両院の意思が一致しないとき、「条約の承認」「内閣総理大臣の指名」「予算の議決」については、衆議院の議決が自動的に国会の議決となります。さらに、予算案については、予算を先に提出する権限(予算先議権)が衆議院に認められています。
しかし、法律案については異なります。法律案は参議院、衆議院どちらからでも提出することができます。また、衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした場合、法律が成立するには、衆議院において出席議員の3分の2以上の賛成による再可決が必要です。
衆議院の3分の2は310議席です。衆議院の定数465議席から与党と対立する野党第1党である立憲民主党の148議席を除くと317議席であり、参議院で否決された場合、衆議院での再可決は難しいのが現在の状況です。
よって、今後、与党が法律の成立を目指すにあたって、参議院で過半数を維持できるかどうかが、重要なポイントとなります。
野党各党の獲得議席数にも注目
ここでは、野党各党の獲得議席数も国会運営に大きな影響をもたらし得ることを解説します。
野党とキャスティングボード
2024年衆議院選挙では、自民党・公明党の議席が過半数の233議席を下回り、与党のみでは予算案や法律案を可決することができなくなりました。それにより、野党第2党・第3党である日本維新の会・国民民主党が「キャスティングボード」を握ると言われました。
キャスティングボードとは、「決定権」という意味です。議席数は与党が計220議席であり、野党第1党である立憲民主党が148議席です。予算案や法律案について与党と立憲民主党が合意しなかった場合、野党である日本維新の会、または国民民主党等が与党に合意すれば、過半数に達し衆議院で可決することができます。
実際に、令和7年度予算案は、日本維新の会が目指していた高校無償化等を予算案に盛り込むことで、日本維新の会と与党が合意し、衆議院で可決しました。
野党各党の獲得議席数が国会運営へもたらす影響
与党が参議院で過半数を下回った場合、衆議院と同様に、第3勢力である日本維新の会や国民民主党がキャスティングボードを握ることが考えられます。その場合、衆参両院で、与党の合計議席数が過半数を下回る与野党逆転となるため、衆議院の議席数に加え、各野党が参議院選挙で獲得した議席数が、与党にとってどの野党と協力を試みるかの判断材料になります。
そのため、与党や最大野党だけでなく、その他の野党の獲得議席数も注目ポイントとなります。
野党共闘の戦略と影響
野党の勢力拡大の可能性が注目されている2025年参議院選挙ですが、ここでは、与党に対抗するための野党の選挙戦略のひとつである、野党共闘について解説します。
野党共闘とは
野党共闘とは、与党に対抗するために複数の野党が選挙協力をすることです。具体的には、候補者調整や相互推薦などがあります。
候補者調整とは、野党の候補者同士が競合しないように、各党の候補者が出馬する選挙区を調整することです。1人しか当選しない選挙区で、与党を支持しない有権者の票が割れることを防ぐため、選挙協力を行う野党間で候補者を一本化することが多くあります。
相互推薦とは、協力する政党の候補者を互いに推薦することです。相互推薦している候補者の応援演説を行うことなどもあります。
野党共闘の過去の事例と課題
野党共闘には、与党を支持しない有権者の票が割れにくくなるという利点がありますが、野党間での調整はしばしば難航することがあります。
2019年参議院選挙では、立憲民主党・国民民主党・共産党・社民党の4党が、改選1人区のすべて32区で候補者を一本化しました。改選1人区とは、定数が2であり、選挙1回ごとの当選者が1人の選挙区のことです。その次の2022年参議院選挙では、野党間での調整が難航し、改選1人区32区中11区のみでの限定的な候補者一本化となりました。
昨年の2024年衆議院選挙では、早期の解散により野党は十分な調整時間を確保できず、一部の小選挙区のみでの候補者一本化となりました。
今回の参議院選挙においても、立憲民主党を中心に、改選1人区での候補者調整が模索されています。しかし、支持が拡大傾向にあるため党勢を拡大したい国民民主党や、関西を中心に勢力を維持したい日本維新の会などを含めた調整は、難航が予想されています。
選挙における党首討論の役割
各党の選挙戦略が注目される中、有権者にとって重要な判断材料のひとつが、党首同士の討論です。ここでは、選挙期間中に行われる党首討論の役割について解説します。
党首討論とは、選挙に向けて、主要政党の党首がメディアの前で討論を行うことです。国会会期中に実施されている、国家基本政策委員会合同審査会にて総理大臣と野党党首が議論を行うことも、党首討論と呼ばれますが、それとは異なるものです。
選挙に向けた党首討論は、各テレビ番組が党首を呼び実施するものもありますが、中でも注目度が高いものが日本記者クラブの討論会です。2025年参議院選挙における日本記者クラブ主催の党首討論会は、公示日である7月3日に先立ち、7月2日に実施されました。自由民主党・立憲民主党・公明党・日本維新の会・国民民主党・共産党・れいわ新選組・参政党の8党の党首が出席しました。
党首討論では、主要政党の党首が重要な政策等について討論を行います。そのため、選挙で争点とされる議題について各党の姿勢が明確化されやすく、有権者が投票先を決める際の参考になります。
まとめ
- 参議院選挙の注目ポイントは、与党が改選・非改選合わせて過半数の125議席を維持するかどうか
- 衆議院が少数与党となっている現在、参議院の過半数は、法律の成立において特に重要になっている
- 参議院選挙で与党が過半数を下回った場合、第2・第3野党がキャスティングボードを握る可能性がある
- 与党に対抗するため、野党間での候補者調整により野党共闘が模索されている
- 主要政党の党首が重要テーマについて議論する党首討論は、有権者にとって投票先を決める参考となる
<参考文献>
「会派名及び会派別所属議員数」 衆議院(閲覧日 2025/03/10)
「会派別所属議員数」 参議院(閲覧日 2025/06/13)
「衆議院と参議院の関係」 参議院(閲覧日 2025/04/14)
「新年度予算案 衆議院を通過 参議院での審議へ」 NHK(閲覧日 2025/03/10)
「【詳しく】自公維 教育無償化など合意 予算案は修正・成立へ」 NHK(閲覧日 2025/03/10)
【関連記事】選挙協力・野党共闘とは?わかりやすく解説|スマート選挙ブログ
「参院選2019データ分析」 日本経済新聞(閲覧日 2025/04/14)
「参議院選挙2022 焦点の数字は 改選過半数など」 NHK(閲覧日 2025/04/14)
「【解説】自・公で過半数の勢いも…衆院選・情勢分析 厳しい選挙戦に」 日テレNEWS(閲覧日 2025/04/14)
「衆議院選挙公示 小選挙区・比例 計1344人が立候補 27日投開票」 NHK(閲覧日 2025/04/14)
「参院選「野党共闘」見通せず カギ握る改選1人区、昨年の衆院選も限定的」 産経新聞(閲覧日 2025/04/14)
「参院選 国民 1人区に積極擁立方針 野党候補の一本化が焦点」 NHK(閲覧日 2025/04/14)
「参院選へ310人超準備=自民、1人区擁立終了―野党一本化進まず」 時事通信ニュース(閲覧日 2025/05/03)
「党首討論 | ねほりはほり聞いて!政治のことば」 NHK政治マガジン(閲覧日 2025/05/03)